親知らずとは?

親知らずは奥歯の中で最後に生えてくる永久歯で、一般的に17〜25歳頃に生え始めます。正式には「第三大臼歯」と呼ばれ、上下左右に1本ずつ、合計4本あるのが一般的ですが、近年はもともと生えてこない人もいます。十分なスペースがない場合、親知らずは横向きや斜めに生えたり、骨の中に埋まったまま出てこないことがあります。その結果、隣の歯を押して歯並びに影響を与えることもあり、歯ぐきや骨に炎症が起きる場合もあります。また、奥に生えるため磨きにくく、虫歯や歯周病のリスクが高まり、口臭の原因になることも少なくありません。
症状がなくても、将来的なトラブルを防ぐために、定期的な確認やレントゲン検査が推奨されます。親知らずの生え方やお口の環境に応じて、抜歯の必要性を判断することが大切です。
このようなお悩みはありませんか?
- 親知らずが生えてきたけど痛みや違和感がある
- 横向きや斜めに生えてきている
- 食べ物が詰まりやすく、口臭が気になる
- 親知らずや周囲の歯の虫歯が心配
- 親知らずを抜いた方がいいのか迷っている
親知らずの治療方針
親知らずの位置や生え方には個人差が大きく、必ずしも抜歯が必要なわけではありません。しかし、横向きや斜めに生えている場合は、痛みや炎症、周囲の歯への影響など、トラブルが起きやすいのも事実です。そのため、抜歯の必要性や治療方針を判断する際には、正確な診断が欠かせません。また、抜歯を行う場合は、痛みを抑えつつ安全に処置することが大切です。当院では、より安全で負担の少ない治療を提供するための取り組みを行っています。
CTの活用
当院では、低被曝・高精度のモリタ製CTを使用しています。従来のレントゲンでは確認しづらい親知らずや顎の骨、神経、血管の位置なども詳細に把握できるため、安全で最適な抜歯計画を立てることが可能です。特に埋まっている親知らずや、神経に近いケースでもリスクを最小限に抑えることができます。
伝達麻酔の使用
麻酔は通常の浸潤麻酔に加えて、必要に応じて伝達麻酔も行います。伝達麻酔は神経の根元近くに薬を注入する方法で、広範囲を効率よく麻酔できるため、痛みをより少なく抑えられます。これにより、抜歯時の不快感を最小限にし、安全で安心な治療を提供しています。
親知らずの生え方
正常に生えている
親知らずがまっすぐ生え、上下の歯としっかり噛み合っている状態です。噛み合わせや周囲の歯に問題がなければ抜歯は不要ですが、奥にあるためブラッシングが難しく汚れが残りやすい点に注意が必要です。定期検診と丁寧なセルフケアで、虫歯や歯周病のリスクを抑えられます。
斜めに生えている
(斜位埋伏)
完全に横ではなく、やや斜めに傾いて生えている親知らずは、歯の一部が歯ぐきから見えることがあります。そこに食べ物が詰まりやすく、炎症や痛みの原因になることもあります。磨き残しによる虫歯や歯周病のリスクもあり、状態によっては抜歯が検討されますが、傾きや噛み合わせによっては経過観察で問題ない場合もあります。
半分しか出ていない
(半埋伏)
歯ぐきに一部だけ覆われている状態です。露出部分と覆われた部分の間に細菌が入りやすく、智歯周囲炎(親知らず周囲の炎症)を起こすことがあります。腫れや痛みを繰り返す場合は早めの抜歯が望ましいこともあります。また、日常のケアだけでは炎症を防ぎにくいため、定期検診が重要です。
完全に骨の中に埋まっている
(完全埋伏)
完全に骨や歯ぐきの中に埋まっている状態で、外からは確認できません。症状がないこともありますが、隣の歯を押して痛みを引き起こしたり、嚢胞(のうほう)ができるリスクがあります。将来的なトラブルを避けるため、定期的にレントゲンやCTで経過観察を行うことが推奨されます。
親知らずの抜歯
判断ポイント
次のような症状がある場合は、早めの抜歯を検討しましょう。特に、炎症を繰り返す場合や周囲の歯に悪影響が出ている場合は、放置せず早めの対応が大切です。
-
炎症が起きていて、痛みや腫れがある
-
歯ブラシが届きにくく、虫歯や歯周病のリスクが高い
-
隣の歯を圧迫していて、歯並びが乱れる可能性がある
-
噛み合わせが悪く、顎や顔に負担がかかっている
-
口臭の原因となっている
親知らずの抜歯リスク
- 抜歯後に、腫れや痛みが出ることがあります。
- 傷口から細菌が入ると、炎症や膿が出る場合があります。
- 下顎の神経が近い場合、唇や舌の感覚が一時的に痺れることがあります。
- 血餅ができず骨が露出すると、痛みが長引くことがあります。
- 長時間口を開けることで、顎関節に負担がかかることがあります。
親知らずの抜歯後の注意点
親知らずの抜歯後は腫れや出血が起こることがあります。回復をスムーズにするため、次の点に注意しましょう。
-
腫れや出血のケア
親知らずの抜歯後は、腫れや出血が起こることがあります。術後は頬や顎の外側を冷やすと血管が収縮し、腫れを抑える効果があります。出血が続く場合は、清潔なガーゼを抜歯部に当てて軽く圧迫しましょう。強く吸ったり、口を勢いよくゆすぐのは、血の塊が取れて治りが遅れる原因になるため避けてください。
-
食事
抜歯後1〜2日は、刺激の強い食べ物や熱い食事は避け、やわらかいものを中心に摂るようにしましょう。おかゆ、スープ、ヨーグルトなどは消化が良く、傷口への負担も少なくなります。硬いものや噛む力が必要な食べ物は、腫れや出血を悪化させる可能性があるため、避けたほうが安心です。
-
生活習慣
術後は、血流が良くなると腫れや出血が強くなることがあります。激しい運動や長時間の入浴は血圧や血流を上げてしまうため、抜歯後1〜2日は控えることをおすすめします。また、十分な睡眠と安静を心がけることで、体の回復も早まります。
親知らずの
よくある質問
-
親知らずの抜歯後、痛みはどれくらい続きますか?
抜歯後の痛みは術後すぐに現れ、2〜3日でピークに達することが多いです。その後は徐々に和らぎ、1週間ほどで落ち着くことが一般的です。痛みの程度は親知らずの生え方や抜歯の難易度によって異なりますが、ほとんどの場合、鎮痛薬で十分にコントロールできます。術後のケアや安静を心がけることで、回復を早めることができます。
-
親知らずの抜歯後は腫れますか?
親知らずの抜歯後は多くの場合、腫れが生じます。特に横向きや斜めに生えている場合は、抜歯の処置が複雑になりやすく、腫れが出やすい傾向があります。腫れは術後1〜2日でピークを迎え、その後徐々に落ち着き、1週間前後で治まることが多いです。体質や抜歯の難易度によって個人差はありますので、腫れや痛みが長引く場合は早めに歯科医師に相談しましょう。
-
親知らずを抜歯すると、顔や歯並びに影響はありますか?
親知らずを抜歯しても、通常は顔の形や歯並びに大きな影響はありません。ただし、歯並びが非常に密集している場合や顎の骨の状態によっては、抜歯後にわずかな変化が出ることもあります。気になる場合は、抜歯前に歯科医師に相談することをおすすめします。
親知らずのご相談

親知らずは、まっすぐ生えて問題のない場合もあれば、斜めや横向きに埋まって炎症や痛みを引き起こす場合もあります。正しい診断が、将来の腫れや虫歯、歯並びの乱れを防ぐポイントです。
当院では、CTで親知らずの位置や形を詳しく確認し、必要に応じてできるだけ腫れや痛みを抑えた抜歯を行っています。親知らずに違和感や不安がある方は、早めにご相談ください。
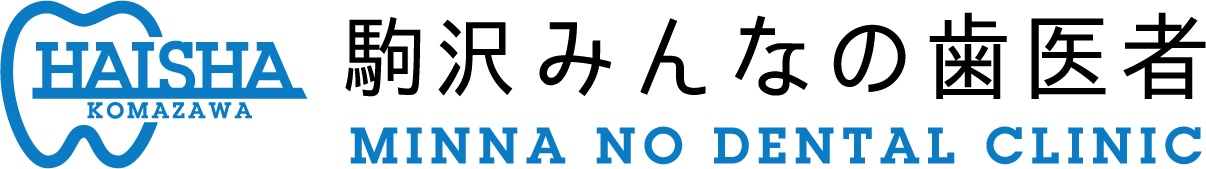



 WEB予約
WEB予約 電話予約
電話予約